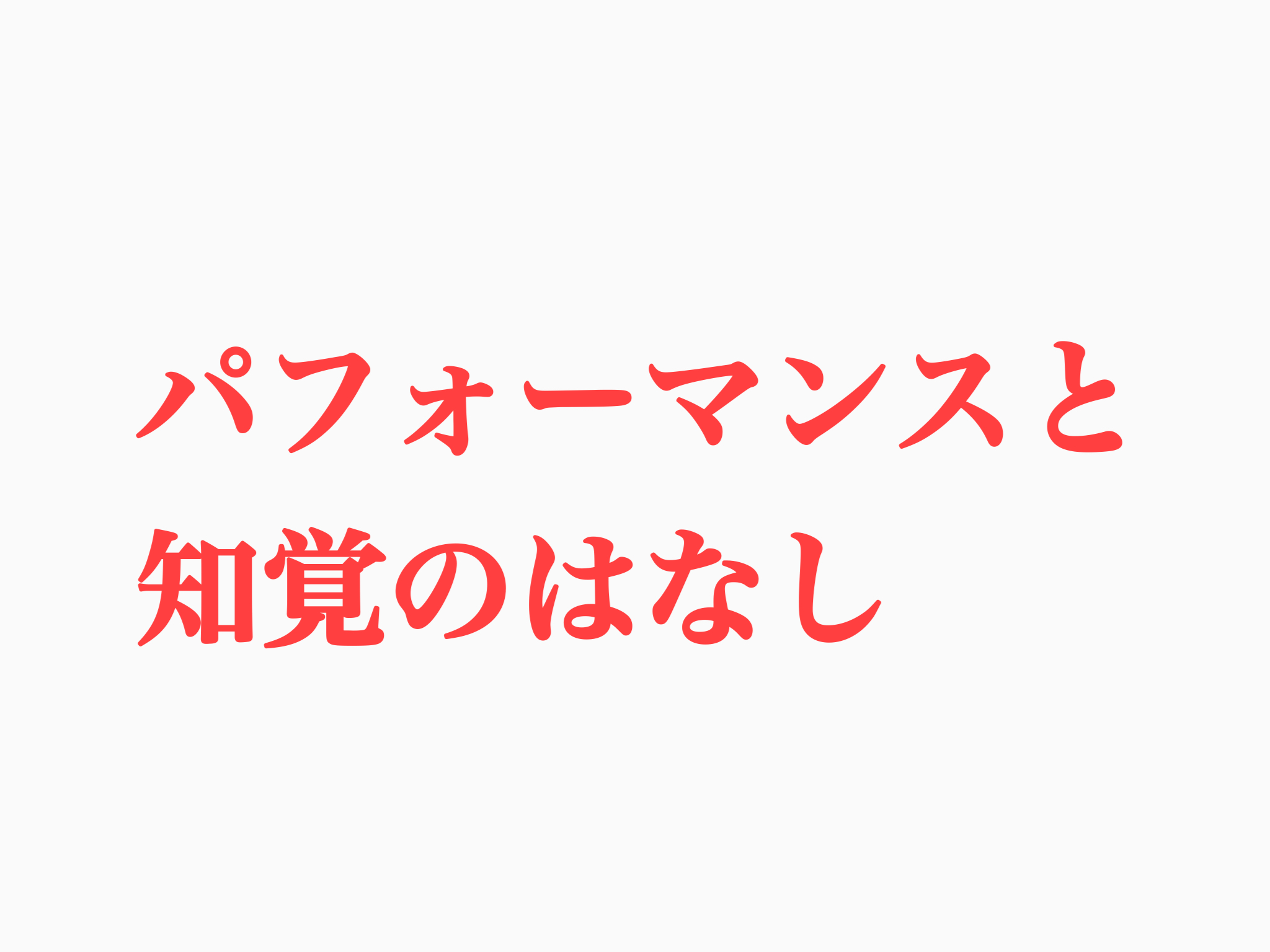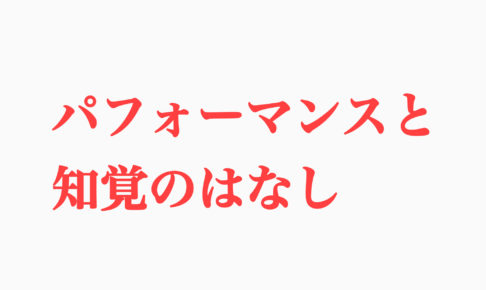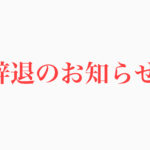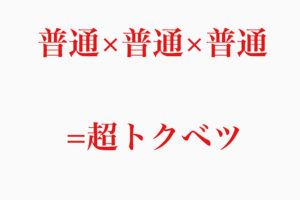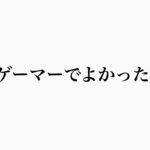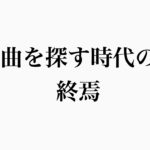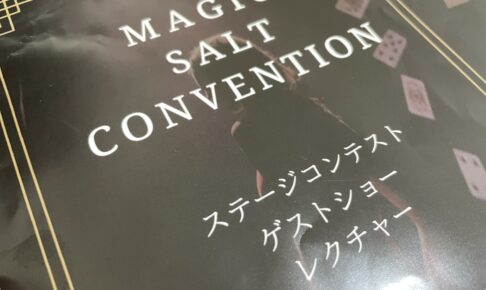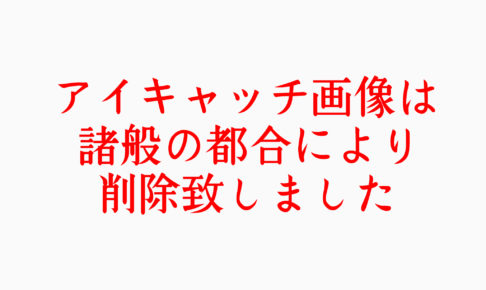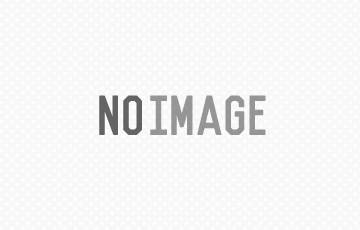パフォーマーの謳歌 Ouka(@performerouka)です。
昨日は不穏な記事をアップすることになりましたが、今回は真面目に芸事の話でもしようかと思います。
*僕個人の見解です。
いわゆる演目というか、ジャンルというか、その言い方にこだわるわけではないのですが、
ちょっといくつか挙げていきましょう。
・ジャグリング
・マジック
・アクロバット
・パントマイム
・ダンス
もっとあるけどとりあえず割愛して話を進めるよ。
さて、これらの演目をふたつのグループに分けます。
分け方は色々あるとはおもうのですが、
僕は
マジック、パントマイム
と
ジャグリング、ダンス、アクロバット
の2種類に分類して考えることが多いです。
どのように分類したか分かりますでしょうか?
密室実験。
ケース1
とあるパフォーマーを密室にひとり閉じ込めたとします。
そこで彼はダンスを踊ってもらいました。
これってダンスを実行したことになりますか?
はい、答えは
「ダンスを実行した」
ですよね。
密室だろうがなんだろうか、ダンスをしたらダンスです。
当たり前じゃん、って思いますよね。
でも待ってください。
次のケースはどうでしょう?
ケース2
今度は密室にひとりのパフォーマーにマジックを演じてもらいました。
この場合、マジックを実行したといえるでしょうか?

まあちょっと待ってください。
マジックは観客に不思議を知覚してもらう芸能です。
そもそもの行為自体、観客がいないと成り立たないのです。
カードを消す、コインを増やす、ぶっちゃけ本当に物理的に物が消失したり倍増しているわけではないのはご存知のとおりです。
(もし本当にしてたら魔法)
カードを消すための技術を行う
と
観客から見て、カードが消えた
は天と地ほどの差があります。
どれだけ難易度があれどれだけの技法であれ、
最終的に観客の「消えた!?」という知覚なしに、カードを消すマジック自体成り立ちません。
お客さんの知覚が、マジックをするという行為そのものにとって必要不可欠なのです。
というわけで、そもそも観客が全くいない場所ではマジックを実行することができません。
マジックの練習、ならできるでしょうけれど。
録画して〜ライブキャストして〜みたいな話はめんどいので割愛します
お客さんが必要な行為とそうではない行為
さっきの思考実験からもわかるように、お客さん(観客)が性質上必要なジャンル、そしてお客さん抜きでも行為自体成立するジャンルがあります。
バク宙はお客さんがいてもいなくてもバク宙です。
そこに透明なロープでもあるかのように錯覚させて見せる、これはお客さんなしに成立しません。
観客なしでも実行できるグループ
ジャグリング
ダンス
アクロバット
実行に観客が必要なグループ
マジック
パントマイム
さて、ここにオブジェクトマニピュレーションを加えてみましょう。
まずオブジェクトマニピュレーションとは何??
って声が聞こえてきそうですが、
こーゆーやつです。
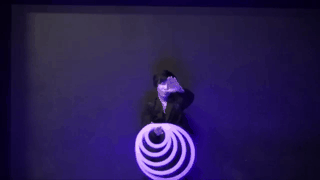
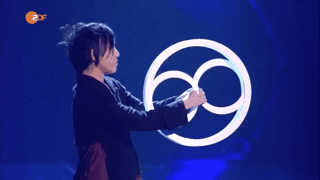
こういったオブジェクトマニピュレーションがどっちに入るかというと、
どちらとしても行うことが出来るのです。
少なくとも私はそう考えています。



はい、僕は後者、お客さんの知覚に重きを置いて演じています。
技術にはこだわりをあまりもってません。
(技術の取捨選択にはそこそここだわり持ってるけど)
ちなみに僕の他に、そういう観点でオブジェクトマニピュレーションをやっている人物として、
ポーランドのshaoを紹介しておきます。
いやホント見てて視覚効果が面白い。
創作しようぜ
「何をやるか?」をベースに考えることがよくあると思います、
でもそれ以上に「どうやるか?」が大事じゃないかと思っています。
ジャグリングをお客さんの知覚ベースで演じたらまた別のものが生まれるかもしれません。
「背中から投げてる、ように見えるジャグリング」なんかが一例ですね。
僕もたまにショーで演じてます。
逆にマジックも「お客さんに不思議さを知覚してもらう」という概念の外、技術をそのまんまやっちゃうマッスルパスやカーディストリーといった新しい概念が生まれています。
発想次第でもっと新たしいものが生まれるかもしれません。
というわけで今回はガッツリ本業の話でした。
ではまた次の記事でお会いしましょう!